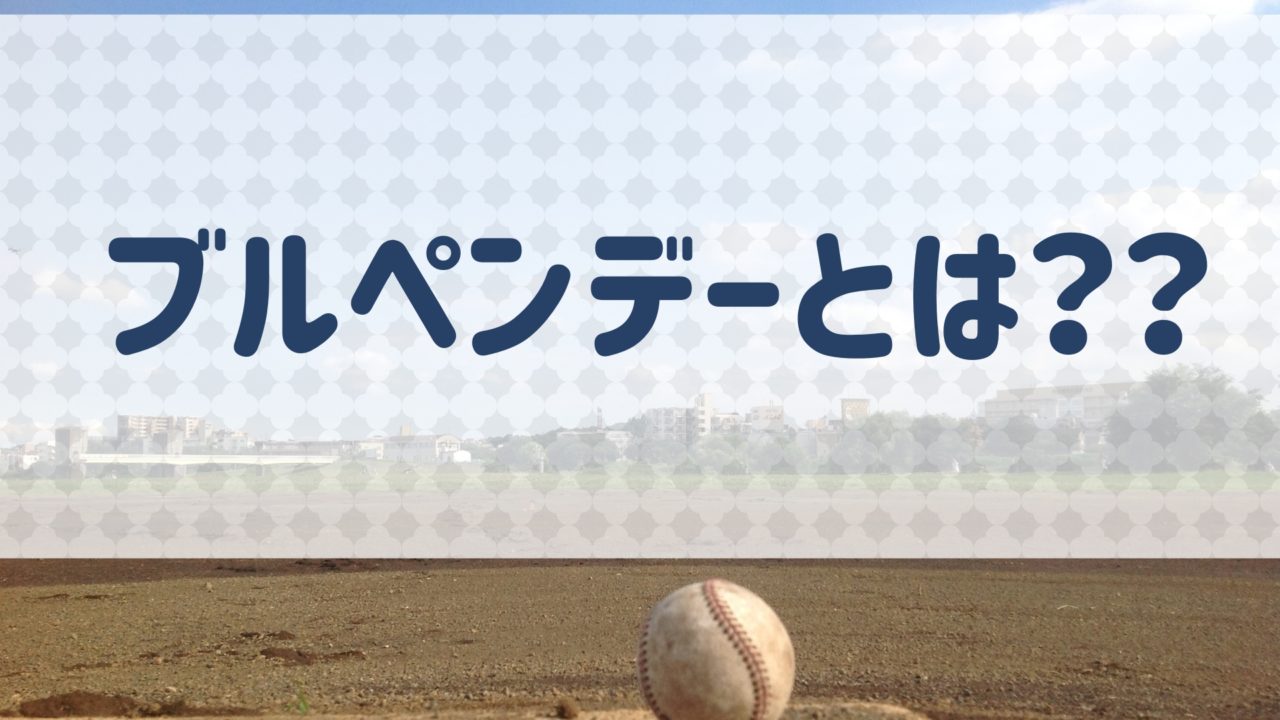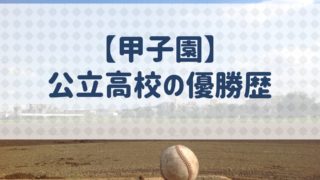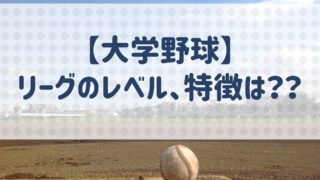年間に140以上もの試合を行うプロ野球や大リーグにおいて、ブルペンデーという戦術が導入されるようになりました。
ブルペンデーとはどのような戦術なのか?
ブルペンデーのメリットとデメリットなどを交えながら解説していきます。
ブルペンデーとは

長いペナントレース。
監督やコーチは計画的にシーズンを戦うために様々な投手起用を考えます。
その主なものに、先発ローテーションを回すオーソドックスな戦略とオープナーと呼ばれる戦術、そしてブルペンデーと呼ばれる戦術があります。
また、北海道日本ハムファイターズの栗山監督が使う、ショートスターターと呼ばれる投手起用法も存在します。
ブルペンデーを解説する前に、まずはオープナーについて触れたいと思います。
オープナーとは、9イニングの中で最も得点率の高いイニングは1回だというデータから、本来、最終回を任される抑え投手を先発にし、上位打線を抑えた後に先発投手がロングリリーフするという戦略のことを言います。
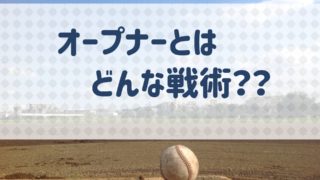
そして、このオープナーが派生した戦術がブルペンデーだと言われています。
ブルペンデーとは、1試合9イニングを先発投手を使わずにリリーフ投手を中心にして小刻みに継投していく戦術を言います。
普段は中継ぎや抑えとして、ブルペンにいるリリーフ投手で試合を行うことからブルペンデーと言われています。
それでは、なぜブルペンデーという戦術が使われるのでしょうか?
ブルペンデーの必要性
1シーズン140試合以上を行う過酷なペナントレース。
常に好調子の先発投手がローテーション通りに機能するとは限りません。
チーム事情にもよりますが、先発ローテーションは日本では5名~6名で構成されます。ペナントレースを戦う中、10試合前後の連戦や先発投手の故障など予期せぬアクシデントも長いシーズンでは発生するものです。
ブルペンデーとは、戦略的に且つ計画的に行うケースもあれば、急なアクシデントがもとで行うケースもあることを覚えておきましょう。
ブルペンデーのメリット、デメリット
メリット
- 先発ローテーションの投手陣の疲労を軽減させることが出来る。
- 小刻みな継投によって打者の目先を変えて的を絞らせない。
シーズン途中で迎える10連戦などの過密日程の中では、計画的にブルペンデーを採用するチームが増えて来ています。
これは先発投手陣の疲労を考慮してのもの。
1日でも多く先発陣を休ませることが出来れば体力も回復し、その後の投手起用も計画的にできるという訳です。
また、現在のプロ野球では予告先発が定着し、次戦の先発投手が右投手なのか左投手なのかを事前に知ることが出来るようになり、結果、対戦相手にとっては左投手の場合には右打者を多く配置するなどの事前準備が出来るようになりました。
しかし、ブルペンデーは小刻みな継投を行うため、打者の左右はあまり意味をなさず、対戦相手に事前準備をさせないという利点もあるのです。
しかしながらブルペンデーにはデメリットも存在するため、多くのチームはそれほど多くこの戦略を使用することはありません。
デメリット
- リリーフ投手間で大きな力の差が存在する。
- 先発をする投手にとっては、負け投手になることはあっても勝ち投手として成績を残すことが出来ない(勝ち投手の権利を持って投げ続けた場合を除く)。
日本のプロ野球を見渡した時に、好投手として思いつく投手の名前をあげてみてください。
その多くが先発投手ではないでしょうか?
リリーフ投手の名前もあがるでしょうが、先発投手と比べるとその数は少ないのではないかと思います。
千葉ロッテマリーンズの吉井投手コーチもブルペンデーで試合に勝利したにも関わらず、自身のブログで
ブルペンデーですが、やってみて頻繁に使う作戦ではないなと思いました。1軍レベルのリリーバーが15人以上いれば多用してもいいかも。
とコメントしています。
つまり、ブルペンデーを多用するためには1軍レベルでしっかりと活躍が出来るリリーフ投手が数多く必要であり、今の中継ぎ陣のレベルや人数では限られた試合でしか使うことが出来ない戦略であることを認めています。
また、井口監督も試合後
ブルペン全員でしっかり投げてくれた。(ブルペンデーは)はやりになってきていますけど、基本は先発がしっかり投げて、抑えに繋ぐこと。(中略)今後はプレーオフとかに入らない限り、おそらくないと思う。
引用:sanspo.com
とコメントしており、あくまでブルペンデーは非常時の緊急策と捉えていることが読み取れます。
ブルペンデーまとめ!
- ブルペンデーはオープナーの派生系
- 【メリット】先発陣の休養、打者の目線を変える
- 【デメリット】リリーフ投手の力、継投策のため先発投手に勝ちが付かない
先発投手陣に休養を与えるなど、ブルペンデーの持つ意味がしっかりと存在することは事実です。
しかし、高いレベルのリリーフ投手が少ない場合には負け試合となってしまう可能性が高くなるため、日本のプロ野球ではなかなか多用するチームが存在しないのも事実なのです。